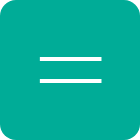公式サイトも“狙われる”時代へ クライアントサイド脅威とブランドセーフティ 〜広告配信の安全性を守るために〜
2025/07/23
寄稿記事
寄稿提供:株式会社Spider Labs
はじめに
「ブランドセーフティ」という言葉は、ここ数年で広告業界に広く浸透しました。広告主や媒体社が、広告配信の場や隣接するコンテンツに問題がないかを確認し、不適切な掲載によるブランド毀損を防ぐ――。
しかし、ブランドセーフティを“広告の掲載面”だけの課題と捉える時代は終わりつつあります。今、自社公式サイト(オウンドメディア)自体が「新たな脅威の発信源」となるケースが急増しています。
公式サイト=ブランドの“最後の砦”
Webマーケティングが進化する中、公式サイトは「ユーザーとブランドの最初の接点」であり、「コンバージョンの着地点」であり、さらには「リピートやファン化の基盤」として存在感を増しています。
現在、94.5%のWebサイトが外部ツールや第三者タグ(広告配信タグ、計測・リマーケティング用タグなど)を利用しており、公式サイト上で“外部コード”を管理・監視することはもはや例外ではなくなっています。
広告主も媒体社も「自社配信のタグが、ユーザーにどんな体験・リスクをもたらしているか?」を今まで以上に意識する必要があります。
クライアントサイドのリスクとは
広告やマーケティングのタグは、ほとんどが「クライアントサイド」――すなわちユーザーのブラウザ上で動きます。
このとき、第三者が提供するタグ(広告タグや計測タグなど)が、意図しない情報の送信や、不正な動作、改ざんのリスクを生むことがあります。
実際、
・外部の広告タグを通じて“乗っ取り”や“情報漏洩”が発生
・配信パートナーが設置したタグが原因で、ユーザーの個人情報が外部に流出
・GTM(Google Tag Manager)等の運用ミスによる、予期しないタグの挙動
といった事例が、国内外で後を絶ちません。広告掲載面のリスク管理だけでは、ブランドの信頼は守りきれない時代です。
実際の被害と業界への影響
国内の大手ECサイトや有名ブランドのオウンドメディアで、「広告タグや外部タグの脆弱性」が原因となった
・クレジットカード情報や個人情報の流出
・不正な広告表示、フィッシングページへの誘導
・偽のリマーケティングや、意図しない外部送信
など、ユーザーや広告主の信頼を大きく損なう事件が発生しています。被害が明るみに出た場合、広告主・媒体社ともに不適切な広告配信・データ管理とみなされ、業界全体への信頼低下にも直結します。
なぜ発生する?―ブラックボックス化するタグ管理
広告タグや第三者タグは、複数の部署や外部委託先によって追加・管理されることが一般的です。
しかし、
・どのページに、どの広告タグ・計測タグが動いているか?
・追加・削除のたびに、きちんと目的や挙動を把握しているか?
・意図しない改ざんや、設定ミスはすぐに検知できるか?
を“常に”確認できている企業・媒体社はごくわずかです。特にGTMやCMSの普及で「誰でも簡単にタグを追加できる」環境が増え、タグ設置の履歴や運用ルールが曖昧なまま、“気づかないうちにリスクが積み重なる”ことが多発しています。
国際基準も「クライアントサイド監視」を義務化
こうしたリスクに対応するため、2025年3月より国際的なセキュリティ基準(PCI DSS v4.0.1)では、クライアントサイドの監視・管理が明記されました。
広告主・媒体社は今後、
・どの外部タグが、どこで、何のために動いているか棚卸し
・改ざんや新規追加をリアルタイムで検知し、不正な動きは即ブロック
・外部送信や異常なタグを自動でレポート・可視化
・こうした運用体制を“継続的に”維持する
といった体制づくりが必須となります。これは決して“カード情報を扱うECだけ”の話ではありません。ブランドを守るため、広告掲載面+公式サイトの両輪で「安全性」を高めることが、すべてのデジタル広告関係者の責任です。
タグ管理の透明性がブランド価値を左右する
・自社が配信する広告タグ・計測タグが“ユーザーにどんな影響を及ぼしているか”
・その管理や検証フローが「外から見て透明」であるか
が、今後ますます問われることになります。「自社広告がユーザーや取引先に“本当に安全”か?」を、掲載面だけでなく公式サイト運用の現場でも追求していくことが、これからのブランドセーフティの本質と言えるでしょう。
明日から実践できる“見えないリスク”対策
・どんな広告タグ・外部タグが設置されているか定期的に棚卸し
・GTMやCMSの管理画面で「追加・削除履歴」や「動作目的」を確認
・改ざんや異常を自動で検知するセキュリティ監視ツールの導入
・新規タグ追加・キャンペーン実施時は必ず“検証フロー”を組み込む
「安全な広告配信」を「安全な公式サイト運用」とセットで考える時代であることを、組織全体で共有することが重要です。
おわりに
ブランドセーフティ=「広告掲載面の選定」だけではなく、「公式サイトを通じた広告・データ配信の健全性」までを一体で守ることが、今や業界のスタンダードです。
ユーザー・取引先・広告主の信頼を守るために、「見えないリスク」を“見える化”し、広告とサイト、両方の安全運用を共に高めていきましょう。